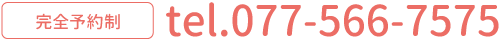TOP > NEWS
NEWS
治療内容のほかに、気持ちや想いもお聞かせください。

妊娠をめぐって、
あなたはどんなふうな軌跡を
たどってらっしゃるでしょうか。
通院しているみなさんも、治療をする側も、
1回1回の治療に
精一杯で臨んでいると思うんです。
ところが、
ベストを尽くしても
結果が出ないこともあります。
中には、何回挑戦しても
なかなか難しい方もおられて、
そういった方が他の病院の治療も経験してみようと
転院されることもあります。
そして、転院先でも、
頑張って治療を続けられ、結果が出ずに、
また戻ってこられることがあります。
どういった治療をされてこられたのか、
結果はどうだったのか、
そういったことは必ず診察のときにおうかがいしていますし
みなさんもしっかり伝えてくださいます。
ところで、
不妊治療をしてきて
どんなことが印象的だったのか、
どんなときに、気持ちがつらくなったりしたのか、
どういう感じで通院していたのか、
パートナーさんとは、どんなふうに支えあえているのか、
気がかりになっているようなことはどんなことか、
というような自分自身の体験について
安心して話せたりシェアできる場所や相手はいますか。
結果が出ることが何よりも大事で
結果さえ出れば苦労は吹き飛ぶように思えますし、
実際そうかもしれません。
けれど、妊娠しても、子どもが生まれても、
治療中のあの想いは自分にしか分からないだろうし
忘れられないという方もおられます。
自分の気持ち、こころ、感じ、想いを飲み込んだり、
無理にポジティブに考えようとしたり、
見ないふりをしようとすることも、
自分自身を守ったり
なんとか治療を続けていくうえで
必要なときもあると思うんです。
でも、一方で、
今の自分自身を
ほんとうのかたちのままで
大切にしていくということも、
できたらいいなあ、と思っています。
あなたのこれまでの、今の、
気持ち、こころ、感じ、想いは
どんな感じでしょうか。
そういったことを大切にする時間を
治療と併せて過ごしてみませんか。
臨床心理士 間塚
ついに!タイムラプスインキュベーターが導入されました!

先月、当院にも、
タイムラプスインキュベーターが入りました。
タイムラプスは、
一定の間隔ごとに撮影した写真をつなぎ合わせて
コマ送り動画にする手法のことです。
インキュベーターは、
受精卵を胚盤胞へ育てる培養器のことです。
タイムラプスインキュベーターは、
培養器に受精卵を撮影できるカメラがついていて、
受精卵の様子を培養器から出さずにモニターで確認できる最新機器なんですよ。
タイムラプスインキュベーターを使用しない場合は、
分割の進み具合や受精卵の状態を確認するために
毎日インキュベーターから受精卵を取り出して
培養士さんが顕微鏡で確認をしています。
このやり方では、
インキュベーター内で一定に保たれている
温度や酸素濃度、二酸化炭素濃度とは
異なった外気や光のもとに受精卵を取り出しますので
受精卵への影響が気がかりではあります。
タイムラプスインキュベーターでは
培養器内の受精卵を
15分に1度撮影していきますので、
培養器から受精卵を取り出さなくても
モニターを見れば分割のすすみ具合を確認することができます。
なので、受精卵にストレスを与えることなく
培養しながら観察ができるのです。
それに、今までは、みなさんに凍結する直前の写真を
お見せしていたと思うのですが、
タイムラプスによって
分割し胚盤胞になっていく過程を
みなさんにも確認していただけるようになりました。
私も見させていただきましたが、
分割が進んでいく様子をみていると
「生きているんだなあ」
という実感がより湧いてきました。
タイムラプスで確認された方は、
一枚の写真で確認していたときよりも
より愛着が生まれたりするのではないでしょうか。
さて、この大切な大切ないのちを
子宮にかえしていきます。
移植をしてから判定までの毎日、
からだの調子を気遣ったり
おなかに手をあてたり
いのちに声をかけたりして
過ごす人がほとんどだと思います。
判定までの毎日って
ものすごく長く感じられますし、
こころも落ち着かないですよね。
そして、判定の日。
残念ながら結果が出なかったときは、
次の周期はどうするかを
決めることになります。
そういうときは
結果をきいたときのショックが
頭もからだもこころも
揺らしていると思うのですが、
きっとみなさん
この動揺をグッと押し込んで
次の周期のことをとりあえず頭で考えて
次のためのお薬をもらったりして
帰られるのでしょう。
次の日だって
何事もなかったかのように装って、
がんばって
仕事に行く人が
多いんじゃないでしょうか。
しばらくはいつにも増して
妊婦さんやお子さん連れの方たちを
目にしたくなくなるかもしれませんよね。
一度子宮にかえした
ひとつの大切な命が
止まってしまったことを知るって
私はとても大きなことだと思っています。
何ごともないふりをするのは
とてもむずかしいと思っています。
気を張っていないと
平常心を保てないような
自分の状態や気持ちを
「そうだよね。そうだよね。」って、
話し合える人や場所があれば
そういうときをやり過ごすのに役に立つと
思ってらっしゃる方は多そうですね。
「次があるよ」
「がんばろうよ」
「そのうち、元気になるよ」
なんて励ましはいらないから、
ただ今の状態や気持ちを大切に
ただただ話ができる時間や
ただただ自分を労われる時間が
あるといいなあと思いますし、
できたらそういった時間を
ご自分のために
もってもらえるといいなあと思います。
カウンセリングは
こころとからだを大切にする時間としても
用意しています。
特に意見を言ったり
無理に深めていったりすることなく、
ただただ自分を大切にする時間としても
ぜひ取り入れていただけたらと思っています。
臨床心理士 間塚
話の聴き方、会話のしかた。

普段の人間関係から思うことなんですが、
自分が話したことについて
「そうだよね。そう思うよねえ。」
と、話し相手が言ってくれると、
安心するような感じがするんですよね。
逆も同じで、
相手の人が話していることから
相手のこころを想像して
「ああ、そう思うのもわかるなあ」という気持ちになって
「そうだよね。」と言うと、
更に相手との会話が深まっていくように思います。
一般的に、
誰かとの会話の中では
充分に相手の意見をきいて
相手のこころを想像するよりも、
自分の意見を言っていることって多いと思うんです。
「それってこうなんじゃない?」
「こうしてみたらいいんじゃない?」
「別に大丈夫なんじゃない?」って。
もちろん
“よかれと思って”
“相手の助けになるかと思って”
意見を言うこともあると思うんです。
そして、そんなふうに言ってもらった意見が
ものすごくこころに響くときもあります。
「ああ!そうかも!そうすればよかったんだ!!」
と、目から鱗みたいなときも
少なからずあります。
一方で、相手に意見を言われることで
もっと話したかったこころの声を
言わずに閉まってしまうこともあると思うんです。
「あなたの意見はいいから
私の話を聞いてよ」
と、口にはしないものの
心の中では思っていることだって
あるんじゃないでしょうか。
どちらかが聴き役になっているときって
「今は、自分の意見よりも、
相手の話を聴くことを
優先したほうがよさそうだ」
という判断があって
成立しているんじゃないでしょうか。
それには、聴く側にゆとりがないと、
なかなか難しかったりします。
自分の意見を言い合える関係性は
とても健康的なんです。
聴いてばっかりじゃ、やっぱり疲れます。
みなさんは
周りの人との関係で
どのような関わりになることが
多いですか?
きっと相手によって
関係性って変わりますよね。
自分が心地よくいられる関係で
いられていますか。
相手の話を落ち着いて聴けるゆとりも
自分の話を充分に話せる関係性も
あってほしいなあと思いますし、
お互いの意見をお互いが伝えあうことを
よしとできる関係性でありたいものですね。
臨床心理士 間塚
パートナーさんとの関係にも深呼吸をいれませんか。

妊娠を願って過ごす中で
パートナーさんと
いろんなことを話し合いながら
すすめておられると思います。
みなさんのお話をおうかがいしていると、
パートナーの存在に助けられているときが
たくさんあるように感じられ、
お互いが自分になかったりできなかったりする部分を
補って支え合っておられるんだなあ、と思っています。
そうやって助けられることもある一方で、
治療で受けるショックに温度差があるように感じたり、
生活についても自分の方が気をつけているなあって思ったり、
私の身体やこころの負担、わかってくれてるのかなって思うことも
少なくないと思うんです。
けれど、
「そういうことを口にするとパートナーはどう思うんだろう?」
と、相手の反応を想像して
遠慮することもあるのではないでしょうか。
お互いを思うからこそ
思っていることを言えなかったり、
相手に求めていることを言ったら
嫌な顔をされたり
怒ったりされて
悲しかったり、
そんなときだってありますよね。
何かに向かって一人で立ち向かうときは
自分ひとりが自分の思うように頑張ればいいのですが、
誰かと一緒に一つのことに取り組むときは
お互いの意思や意見を尊重しながら
すすんでいくことになります。
もしかしたら、ある程度の妥協といいますか、
今の相手との間では “どうしようもないこと”を
抱えながらすすんでいかざるをえないときも
あるように思っています。
みなさんは、パートナーさんと、
どんなふうに歩んで来られましたか?
臨床心理士とのカウンセリングでは
そういったお話もおうかがいしています。
みなさんの中には
「相談したって、状況は変わらないと思う」
と思う方もおられるかもしれません。
私たちは、自分が置かれている状況や
自分の本当の気持ちについて、
どんなことでも語れる関係の中で
否定されることなく語れると、
がちがちになっていた心身がほぐれたり
安心感がうまれたりします。
また、お話していく中で
「こんなにパートナーが大事だから傷ついていたんだ!」
「話してみてわかったけど、こういうパターンのときは言い合いになりがちだなあ…」
と、一人では気づきにくかったことに
気づいていかれることもあります。
そういったこころの変化や気づきが、
通院期間の心身の状態や
パートナーさんとの関係性などが、
自分にとってできるだけ親和性のあるものになっていくことに
つながっていくと思います。
そんなふうに
こころにも深呼吸を取り入れながら
過ごしていきませんか。
臨床心理士 間塚
「なんで妊娠しないの?」への答えについて

なにか心配なことがあったときに
ネットなどで調べる方は
とても多いと思うんです。
特に、思いがけない出来事があったり
なかなか思ったようにいかないときは、
どうしたらいいのか
もしくは、どうしてうまくいかないのか、
調べようとすることは
ものすごくあたりまえなことだと思うんです。
こういった行動について
とある臨床心理士の方が
“ 自分の主体性を守ろうとする働き ”
と、説明されていました。
なかなか妊娠に至らなかったり
流産になると、
「なんでだろう?」
って、誰もが思うと思うんですよね。
それで、その「なんでだろう?」を解決するために、
こういう状態になる原因について知ろうとするのだと思います。
通院を始めるきっかけは
「妊娠しにくい原因があるのかどうか知りたいから」
ということがとても多いです。
ただ、妊娠のための検査というのは、
限界があります。
また、何か影響していそうなことが見つかったとしても
それが全てではありません。
どういうことかというと、
例えば、精子が少な目だったりするとしても、
それは検査できる範囲で分かっただけであって、
検査できないところで
他にも影響があるかもしれません。
また、例えば、
「年齢的に、確率は低いんですよ」
「おそらく、受精卵の染色体異常だと思いますよ」
「こういう原因が見つかりましたよ」
などと、現状に対してある程度の説明がついた場合も、
納得ができない気持ちになられることもあります。
それはきっと、
「でも、どうして、私に、
こういうことが起こるのだろう」
というお気持ちなんだと思います。
「何%くらいの確率で、こういうことが起こるので、
あなたがたまたま、この確率に入っただけですよ」
と言われたところで、
「なんで、私が、この確率に入らなきゃいけないんだろう…」
という思いが引っかかる…。
この「なんで」に対しての答えは、
どこかに用意されているのものではなくて、
きっと、ご自分の中で、
どんなふうに折り合いをつけていくかというところで
答えになっていくのではないでしょうか…。
どうぞ、自分のこころを守りつつ、
自分のこころがして欲しそうなことを
たくさんしてお過ごしください。
また、いろんなことを考えたり、
自分を労ったり、を繰り返していく日々の中で、
思っていることを話せる誰かと過ごす時間が
役に立つことがあると、
私は思います。
私たちのクリニックではそういった時間を
カウンセリングという名前で用意しています。
こころを大事にする時間を共にして、
ご自分の中での折り合いを
一緒に探していけたらと思っています。
臨床心理士 間塚
開院14年目を迎えて。

当院は、この9月で開院14年目に入りました。
今日まで、たくさんの方が来てくださり
たくさんの方が卒業され、
周りの方にクリニックを紹介してくださったりと、
みなさんのおかげで
今の草津レディースクリニックがあります。
今現在、通院されている方、
妊娠して卒業された方、
卵子提供や養子縁組などの選択をされた方、
通院をやめる選択ができた方、
より自分に合ったところを求めて行かれた方-。
当院での体験や印象って、
お一人おひとり違うものと思います。
あなたにとっては
どんな体験でどんな印象があるでしょうか。
もう来られる予定のないみなさんは、
その後、どんなふうに時を重ねておられるのでしょうか。
通院されているときは、
妊娠のことが「人生初めての挫折」のように
感じられた方も多かったと思います。
そういうことがあったのですから
できたらその後は穏やかに幸せにと願うものの、
人生そうはいかないものだったりしますよね。
困ったりつらかったりしたときは、
頼れそうな人に頼ったり
ちゃんと休んだりしながら、
ご自分を大切に日々を過ごしてください。
もしよろしければ、子宮頸がん検診などで
お顔を見せてくださいね。
通院するかどうか迷っておられる方は
たくさんおられると思います。
仕事との両立が心配だったり、
原因が知りたいけど見つかったらどうしよう…と複雑な気持ちだったり、
不妊治療を自分たちがするということに気がすすまなかったり
いろんな想いがあると思います。
悩みますよね。
いろいろ考え出すと
出足は鈍ってしまうものです。
「やっぱり、次、生理が来たら考えよう」
って、先に送ってしまいがちですよね。
(そして、このサイクルを繰り返す人もいます)
妊娠へのアプローチって
お二人で決めるものなので、
通院しないならしないでいいんですよね。
そのことについて誰かに何かを言われる筋合いなんて、ないんです。
ただ、もし迷っていたり、
原因があるのかどうか気になっていたり、
いつ排卵しているのか知りたかったりするようならば、
一度来られてみるのもひとつかなと思います。
だって、いつだってやめられますし。笑
一度来てみて、
いつも頭の中で考えている気がかりも含めて
私たちにお話いただくと、
お答えできることはお答えしますし、
一緒に工夫を考えていけると思います。
初めて受診するときは
ちょっと勇気がいるかもですが、
その勇気が安心に変わるんだったら
勇気の出番かもしれません。
それでは、14年目の草津レディースクリニックで
お待ちしております。
臨床心理士 間塚
乗り切れた自分を褒めましたか?

***************
「友達が妊娠したって聞いた….。
ちょっとびっくりして、
すぐにおめでとうって言えなかった。」
「友達から久しぶりに連絡来て会って、
『ああ、やっぱりなあ…』って。
なんか、もう傷つきたくないから
そうかもしれないって思って覚悟して会った。
だから、表面上は、
ちゃんと笑っておめでとう、できた。」
***************
他人のことは他人のこと
自分のことは自分のこと、
そう頭では思っているのだけれど、
気持ちがついていかない時ってあります。
別にね、そんなに無理に
頭で考えていることを
こころに言い聞かせようとしなくても
いいんだと思います。
こころで感じていることも
本当のことだからです。
「おめでとうって言うのが遅れた自分」も
「笑っておめでとうと言えた自分」も、
どちらもすごかったと思います。
突然、大きな荒波が押し寄せて、
舵のコントロールが効かないかも!という状態になったときに、
それに備えて、前もって用意していたり、
戸惑いながらもなんとか乗り切ってみせたり、
すごい力だと思うんです。
そんなふうにできた自分に
「すごいね、がんばったね」
と、褒めてあげましたか。
こういうときに
「友達に心からおめでとうが言えなくて…」
と、自分にガッカリされる方が多いのですが、
いやいや、とんでもありません。
ものすごく頑張ったじゃないですか。
きっと、友達の報告にこころが引っかからずに
喜べる自分でいたかったのだとは思うのですが、
「乗り切られて、本当にすごいですね」
と、みなさんに敬意を表したいと私は思います。
もし、「え?そんなふうに考えたことなかった…」
と、思われた方がおられたら、
今からでも自分に
たくさん声をかけてあげてください。
「すごいね」
「がんばったね」
「ありがとうね」
「がんばってくれてたことに気づかなくてごめんね」
妊娠希望中に落ち込んだりすることって
どうしてもあるなあ、
と思うんですよね。
そのたびに、自分ってちゃんと
がんばって乗り切っていると思うんです。
みなさんは本当にすごい!と、
みなさんのお話をおうかがいしながら私は思っています。
臨床心理士・公認心理師 間塚
妊娠のこと以外の時間の大切さ。

なにかすごく意識してしまうことがあると、
からだが緊張したり
こころが疲れたりすることがあります。
考えすぎはよくないっていうのは、
みなさん、よくご存知なことで…。
できるんだったら
考えないようにするんですけど、
気づいたら考えちゃっているってことも
ありますよね。
妊娠のことも
「考えすぎちゃうんです」
「気になっちゃうんです」
とおっしゃる方はとても多いんです。
すぐスマホで検索しちゃったり、
気づいたら30分、1時間と検索しちゃってた!
なんてことも、珍しくないと思います。
さて、妊娠のことをどうしても意識してしまう毎日を
なんとかしのいでいくために、
3つくらい、妊娠とか関係のない生活場面や
没頭できるものがあるといいそうなんです。
いかがでしょう。
何か、妊娠のことを考えずに過ごしている時間って
思い浮かびますか。
お仕事されている方は、
仕事中は、妊娠のことを考えなくていいって
おっしゃいますよね。
お仕事と通院の両立が大変な場合もあると思うのですが、
お仕事をしていることで助かることもあるんですよね。
他には、どうでしょう。
何か、「楽しかった~!」って思えたり、
もしくは、気分に大きな変化がなく、たんたんと過ごせるような
そんな時間があったらいいなと思うのですが、
そういった時間を過ごしておられますか。
なにをしても考えちゃうなら
早く寝てしまうのも一つかもしれませんね。
(考えすぎているときは眠れないのが常ですが…)
今はなかなかできないけど
前に好きだったこととかを
久しぶりにやってみると、
意外とハマった!
なんてことがあるかもしれません。
願いが叶う確率をあげるために、
何かできることを調べて
取り組んでいく姿勢も、
とても大事なこととは思うのです。
けれど、妊娠は、
いつ願った結果が出るのか
誰にも分からないことなので、
自分が機嫌よく暮らしている時間があることって
きっと支えになると思うんですよね。
結婚生活で
独身のときとは環境が変わって、
やらなきゃいけないことが増えたり
やりたいことができなくなったり、
なかなか思うように暮らせないと
感じている方もおられると思います。
今の自分は
願いが叶うこと以外に
どんなことがあったら
ちょっと喜びそうでしょうか。
どんなことがあれば
気持ちが落ち着く時間が増えそうでしょうか。
そういった時間は
どんな工夫をすれば
あなたのものになりそうですか。
結婚後の難しさもあるかもしれませんが、
そういった時間を
積極的にもてるといいなあ、と思っています。
臨床心理士・公認心理師 間塚
なりたい自分になるために。

今年は行動規制がない夏ですが、
コロナの情勢から
「帰省は控えることにしました!」
という話をチラホラお聞きしていました。
会えない気遣いもあるかもしれませんが、
会うと少なからず気を遣うことになるでしょうし
妊娠のことを詮索されずに済むので
気持ちが楽な部分もあるかもしれないですね。
ところでみなさん
“こうなりたい!”という自分ってありますか?
“なりたい自分に近づくために
どうしたらいいんだろう?”
この間、研修で、
そういったテーマのセッションを受けてきました。
なので、今回は、
そのことをご紹介したいと思います。
ます最初に、
「こういう私になりたい!」って
目標を設定します。
そして、今の自分の現状を把握して
目標とどんなギャップがあるのか認識します。
それからね、
このギャップはどうやったら埋まるのか、
何があれば埋まるのか、
そういうことを考えるんです。
そして、そのことを行動に移していくと、
目標へ近づいていくそうです。
私は臨床心理士の講師の方に
ガイドをしてもらって、
この目標設定をして
現状を確認して、
ギャップを埋めるために
どうしていったらいいのかを考えました。
まず、目標を設定するときに
「こういう私になりたい」自分はどんな自分なのか、
具体的にイメージするといいと思います。
例えば、私は、
「臨床心理士としてもっと成長したい」
と、最初に設定したんですけども、
講師の方に
「もっと成長した自分ってどんな自分ですか?
解像度をあげて教えてください」
と、言われ、
なりたい自分がより明確に鮮明になりました。
なので、より具体的に、言葉にしたり、
丁寧に絵にしてみたりするのがいいと思います。
そして、今の自分のことを、
自分ではどんなふうに感じているのか、確認します。
ネガティブな感じ方からも
ポジティブな感じ方からも
今の自分自身を捉えてみましょう。
それから、目標を叶えるために
どうやったらいいのか、
何があったらできそうなのか、
はたまた、何かを手放したらできそうなのか、
じっくり考えます。
今と目標とのギャップを埋める手段は
今の自分ができそうなことで設定しましょう。
できないことを手段にしちゃうと
進めなくなりますので。
(もしくは、進みたくないっていう
答えが出ているのかもしれませんが…)
できそうなことと、目標との間に、
大きなギャップがある場合は、
その目標に近づくために
まず目先の目標をたてると
いいかもしれませんね。
そしてその目先の目標とのギャップを埋めるために
今の自分ができることを考えましょう。
本当に今の自分に大切なルートを出せると
自分がより喜んで生きることに
意識して取り組めると思います。
どうぞ、じっくりお時間とって、
想像してみられませんか。
私が研修を受けた感想は、
もちろん一人でもある程度は考えられるのですが、
ガイドをしてもらいながら考えると
一人で想像していたのとは
違った方向に落ち着いて、
その落ち着きどころが心地よかったということです。
より今の自分に
大事なことが
クリアになりました。
きっとガイドが
臨床心理学に基づいたアプローチだったことも
大きいと思います。
ご興味がおありの方は、
私がガイドをすることもできますので、
カウンセリングのご予約をおとりいただいて
目標へのルート探しにいらしてくださいね。
臨床心理士・公認心理師 間塚
男性にとってのタイミング療法。

妊娠を目的としたセックスが
うまくいかなかったり
作業のように感じているカップルは
少なくないんですよ。
この間、聖隷浜松病院の泌尿器科医である
今井伸先生の男性不妊についての講演を聴いたのですが、
男性が膣内で射精に至る過程で、
勃起して、その勃起を持続させるためには
リラックスさせる副交感神経を優位にする必要があって、
射精は、反対に交感神経優位のもとで行われるので
高い集中力が求められるそうなんです。
1回のセックスで
リラックスから集中への切り替えがうまくいかなければ
膣内射精はむずかしいということなんですね。
プレッシャーを感じると、
まず勃起に影響が出るそうです。
妊娠のためのセックスのときは
「今日は妻のためにも、射精しなきゃ!」
「子どものために、今日は絶対に!!」」
など、少なからず意気込んでしまうこともあるかもしれませんが、
そういう状態だとリラックスには遠いですよね。
女性側としては
排卵に合わせてタイミングをとるために
毎朝基礎体温を測って
排卵検査薬を毎日試したり、
仕事や予定を調整して通院して
毎回の内診も受けたり
お薬飲んで注射をしているのだから、
その日は最後までいってほしいものですよね。
そして、男性側は、
そういった女性の気持ちを想像して
余計にプレッシャーを感じてしまうところがあるのでしょう。
今井先生は、
女性が男性の気持ちを想像しやすいように、
こういった例示を出されていました。
“もしも、女性がオルガズムに達しないと
排卵しないと仮定します。
指定された日にセックスをして
確実にオルガズムに達する自信はありますか。
これが妊活中の男性の日常なのです。”
参照:「男性不妊症の診断と治療」
不妊症・不育症ピアサポーター等の養成研修より抜粋
女性はもしかしたら
男性は“射精してあたりまえ”
“射精したい生き物”みたいに
イメージしている方がいるかもしれません。
けれど、そうではないんですね。
タイミングをとってと言われた日に
セックスができないことで
ケンカになったりギスギスしたりすることって
よくあると思うんです。
でも、それってきっと、
どちらかが悪いというわけではないんですよね。
そもそも、“この日”って決まっていること、
それで今周期の結果が左右されてしまうこと、
そういう仕組みのせいなんだと思います。
それと、現代の日本は、
セックスの回数が少なくて
セックスの満足度が低い傾向にあるそうなのですが、
そういったところも影響していますよね。
セックスの話は
友達に話す機会があっても
なかなか具体的に込み入った事情を話す場がないようで、
当院で状況をおうがかいしたときに
「話せただけで、安心しました。
どこで相談してもいいんかわからなくて」
と仰られるかたが(カップルが)
珍しくありません。
きっと、毎周期毎周期、
排卵前が憂鬱になったり
カップルの雰囲気が悪くなるほど
ご自分の中で抱えておられたんだと思います。
妊娠に向けて
どうしていったらいいのか、
お二人にとって
どうしていったらいいのか、
何か前向きな話し合いができると思います。
よかったら、話しにいらしてくださいね。
公認心理師・臨床心理士 間塚